睡眠途中目が覚めるけど...もう気にしない

睡眠途中目が覚めたのですが、
思考を変えてみました。
もう開き直って、
「途中目が覚めて寝られない」と思うのではなく、
気にしないことにしました
いつも、
0時前には布団に入るようにしています。
ですが、昨晩、
音楽を聴きあさっていたら、
音楽熱が蘇って熱くなり、
布団に入ったのが
午前2時になってしまいました。
就寝リズムが狂ってしまったので
これはいただけません(涙)
とはいえ、全てが悪い話ではないです。
音楽が聴けるようになったことは、
かなりの好転です。回復している証拠です。

休職する前は、
音楽がただノイズにしか聞こえず、
全く楽しんで聴くことができなかったからです。
休職して身体を休めた結果、
音楽を楽しめるまで
回復した証拠です。
これは非常に良いことです。
いつも決まった時間に中途覚醒。変なリズムになってます
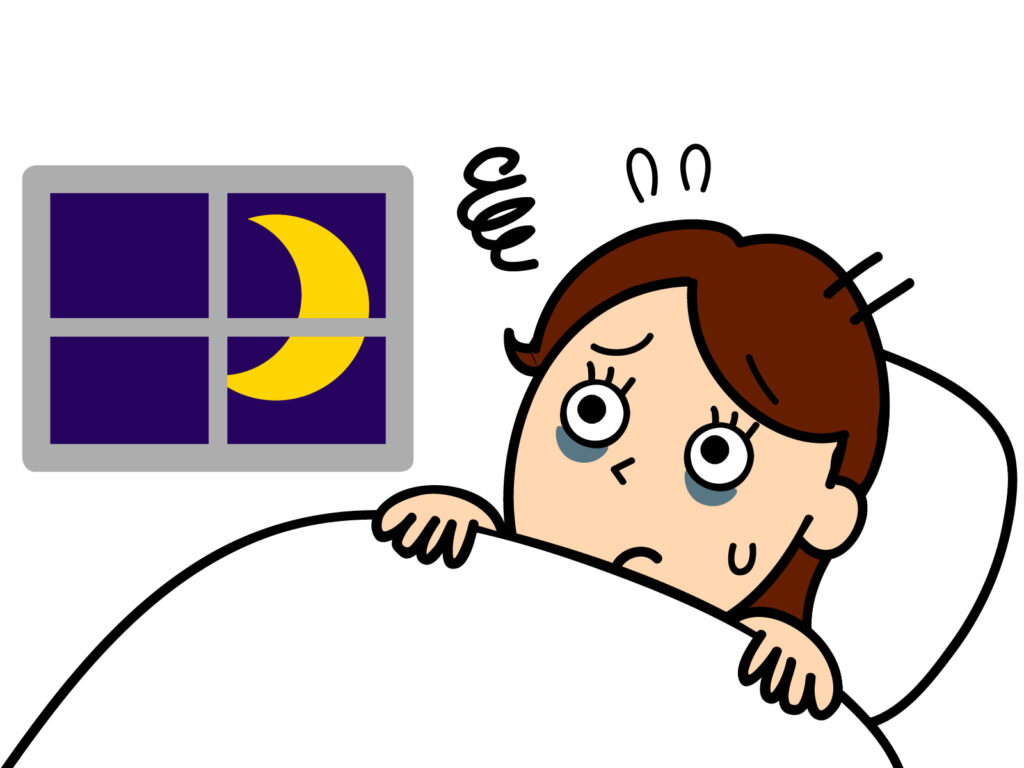
確かに、現在私は睡眠に問題があります。
でも、起きてから
頭はスッキリしているので、
そこまで深刻とは思わないことにしました。
今日は2時に寝て4時ごろに中途覚醒で目が覚めたのですが、
最近は0時に寝て4時に目が覚めています。
どうやら今の私の身体の設定は、
「4時に目が覚める」
というものになっているらしいです。
妙なリズムになっています。
「しっかり寝たいなー」とは思いますが
「寝なきゃ!」とは
あえて思わないことにしています
中途覚醒 横になっているだけでも身体は休まる?

同じく睡眠に問題を抱える友人曰く、
「人間は目をつぶって、
ただ横になっているだけでも、リラックス出来る」
とのことでした。
睡眠をスコア化すると、
普通の問題ない睡眠が100だとしたら、
横になるだけでも70だそうです。
「だらー」としているだけでも
身体は休まるそうです。
寝られずにドギマギするくらいであれば、
「横になるだけでも休まる」を信じてみることにしました。
目が覚めた午前4時
「そのうち身体が眠たきゃねるっしょ」って
開き直って、目をつぶっていたら、
気付いたら7時半でした。
ほら寝れたでしょw
焦って寝ようとすると、
絶対にそれがストレスになってしまいます。
余計目がさえてしまいます。
開き直りって大事です。
目をつぶるだけで休まる理由

目をつぶって、
横になるだけで休まる根拠をチェックしてみました。
視覚からくる、大量の情報量をカットするので
休まるらしいです。
『素朴な疑問です。眠れないとき目を閉じて横になるだけでも休まるというのはどういう根拠があるんでしょうか?』に対して、
日本健診財団の監修のもと、以下のように解説した。目から入ってくる情報をシャットアウトすることで脳が休息できるということではないでしょうか。
引用:眠れない時、目を閉じて横になるだけで休まるというのは根拠はあるの? 医師が回答
人は目から入る情報は非常に多く全体の8割以上ともいわれております。それだけの多くの情報をシャットアウトするわけですからその間脳を休めることができるとはいえそうですね。
「〜しなきゃ」は危険な考え

モノは捉えようです
心療内科での、
カウンセラーさんとの会話を応用してみました。
「〜しなきゃ」をやめる
です。
「睡眠の質が悪い、ちゃんと寝なきゃ」と思うのでなく、
起きた時にスッキリしてれば
「まぁこれでいいかな」と
お気楽に思うようにしました。
人間は1日に35,000回判断をします

黙っていても人間一日に
何回も無意識に決断をしているらしいです。
その数はなんと35,000回!
黙っていても
常に頭を使って判断をしています。
だからこそ、
自分を傷つけたり、
責めるたりするような考え方は
やってはいけません。
無意識でも癖になって
そのような考えをしていたりします。
適応障害の治療薬はありません。
今までの自分の考えの癖に気づき、
変えることが
今後の自分のメンタルを守っていく
武器になります。
自然な目覚めには断然「光目覚まし」
けたたましい音で目覚めるだけが
目覚まし時計と思っていませんか?
日本では音で起きる習慣が当たり前ですが
欧米では
光で起きる習慣もあります。
高緯度の国では、
白夜や逆に極夜(太陽が1日上がってこない)の
地域もあります。
体のリズムを整えるために
太陽と同じ強さの自然な光を浴びれば
体内リズムも整い、
スッキリと目覚められます。
さらに今では後継機も登場しています。
価格は「トトノエライト」の半額ほどです
我々ユーザー側としては
手が届きやすいという点で「価格」は大事です。
サイズ感とか詳細機能など異なりますので
お財布事情もさることながら
自分にとって必要な機能を満たしているのであれば
安い方を選択するのが賢明です。
下記リンクから詳細を確認してください。
こちらもCHECK
-

-
適応障害患者 幼少期の影響もあるの?
思考のクセでメンタル病みます 適応障害は( 適応障害:治療の3原則 )でも語ったのですが、適応障害の治療には三原則があります。 https://hirowata.com/ad-3-prinsiple/ ...
続きを見る


